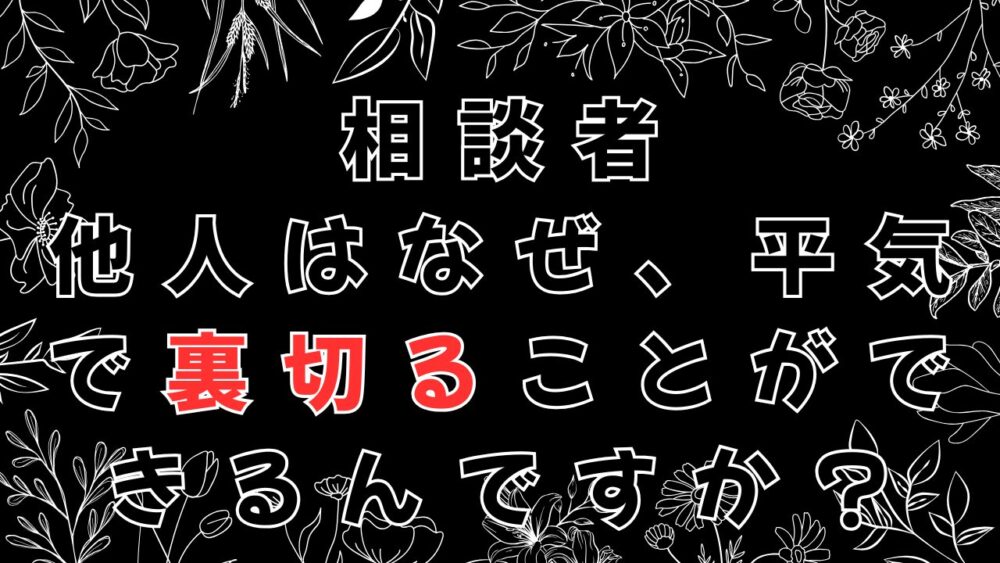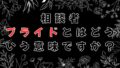相談者
人はなぜ裏切るんですか?
彼女が急に新しい彼を作ったり、
今までの感情や経験を簡単になかったことにできるんですか?
また、
仕事で噓の情報を流されたり、
次は君が出世する番だと言われ、
本当はその人が出世したり、
なぜ、
そんな意地悪ができるんですか?
裏切られる人が悪いんですか?
どうしたら、
裏切りに耐えることができますか?
僧侶
あなたの質問はとても深く、
感情的にも揺さぶられるテーマです。
順を追って、
心理学・仏教の両面からお答えします。
1.人はなぜ裏切るのか

心理的な理由
●自己利益の優先
多くの人は「善悪」より、
「得か損か」で動きます。
感情や信頼よりも、
自分の立場や名誉やお金、
つまり、
利益や安全を優先してしまうのです。
●感情の変化は早い
恋愛感情や友情は「永遠」を誓っても、
刺激・環境・欲求によって急激に変化します。
●嫉妬や競争心
仕事での裏切りや意地悪は、
嫉妬・ライバル心・優越感。
つまり、
自分が上でありたい。
下にはなりたくない。
という感情から、
起きることが多いです。
仏教的な理由

●無常(むじょう)
人の心は常に変化し続けえるという教え。
昨日の味方が今日の敵になるのは珍しくありません。
●貪・瞋・痴(とん・じん・ち)
欲望(貪)、
怒り(瞋)、
愚かさ(痴)
が揃うと、
人は平気で他人を傷つけます。
●業(ごう)
その人の言動は、
過去の習慣・価値観・行動の積み重ねによるもの。
裏切りもその人の業(カルマ)の表れです。
2.裏切られる人が悪いのか?

仏教では、
「原因と縁」の組み合わせで物事が起きると考えます。
裏切りは裏切る人の心の状態が原因であり、
同じ会社にいたとか、周りにいたとか、
そういった縁はありますが、
あなたが全面的に悪いわけではありません。
ただし、
「相手を過信しすぎる」
「危険なサインを見逃す」など、
自分側の選択が縁になることもあります。
これは罪ではなく、
あなたの未来への「学びの材料」として、
活かせば良いのです。
3.裏切りに耐えるための心の持ち方

事実と感情を分ける。
「裏切られた事実」と
「それによって生じた怒りや悲しみ」を
別々に見ると、
心が少し軽くなります。
●「相手の行動は相手の問題
裏切りは、
裏切った人の心の未熟さ、
価値観の低さの結果であり、
あなたの価値を否定する証拠にはなりません。
●無常を受け入れる訓練
人の心は変わるものだと、
そもそも前提で考えておくと、
「まさか…」
の衝撃が少なくなります。
●信頼の段階を設ける
初めから全面的に信用せず、
時間と行動を見て少しずつ信頼を広げる。
どんな人かを知る、判断ざいりょうとして、
初めからあなたのことを教える必要はなく、
相手にしゃべらせて、情報を得ていきます。
●支えとなる軸を持つ
仏教では、
「自灯明(じとうみょう)」=自分を灯(あかり)
とすることを勧めます。
つまり、
自分軸のことです。
他人の態度で心を左右されすぎないよう、
自分の価値基準を育てる。
自分軸を決めて、性根を育てます。
生き方の方向性を決めるということです。
4.仏教的な回復の視点

●忍辱(にんにく)
屈辱や不正を受けても、
怒りを増やさない修行。
●随喜(ずいき)
他人の成功を共に喜ぶ心。
裏切った相手にも同様に、
成功を喜ぶ修行。
●因果
裏切りは必ずその人に返る。
あなたが報復しなくても、
業は巡る。
仕返しを考えない修行。
まとめ

裏切りは相手の心の未熟さと環境によるもので、
あなたの価値を下げるものではない。
無常と因果を理解すると、
怒りや悲しみが和らぐきっかけになる。
信頼は段階的に育てることで、
裏切りの衝撃を減らせることができる。
相談者
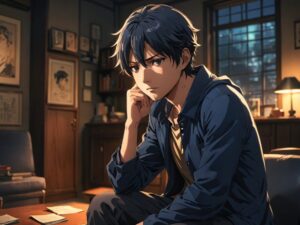
人は損得勘定や自分を守ろうとするときに裏切るんですね。
でも、
子供のころから、
人を裏切ってはいけないと教えられてきました。
なぜ、
大人は子供に対して注意するのに、
自分では守れないのですか?
僧侶
そうですね、
人は「損得勘定」や「自分を守る本能」が働くと、
教わった道徳を簡単に裏切ってしまうことがあります。
ではなぜ、
大人は子供に「裏切ってはいけない」と教えながら、
自分では守れないのか、
これにはいくつかの理由があります。
1.理想と現実のギャップ

子供への教育は「理想」をベースにしています。
「正直であれ」
「嘘をつくな」
「裏切るな」
という教えは、
社会や人間関係を円滑にするための基本ルールです。
しかし大人になると、
現実では、
損得・立場・安全といった要素が複雑に絡み、
理想をそのまま貫くと、
自分や家族が不利益を受ける場面が出てきます。
自分の生き方や誇りを捨てて、
保身への選択が大きくなっていきます。
2.自分への甘さと正当化

保身を選択した人は、
自分の行動を正当化するために、
「これは裏切りじゃない、仕方ないことだ」と
自分に言い聞かせます。
特に大人は経験が多いぶん、
道徳より現実を優先する理由を作るのが上手になります。
3.恐れと保身

立場や収入、
社会的評価を失う恐れがあると、
人は自分を守る行動を取りがちです。
それが結果的に裏切りになることもあります。
子供は守るべきものが少ないため、
純粋に「裏切ってはいけない」という、
価値観を持ちやすいのに対し、
大人は経験が増えていき、
選択肢が増えていき、
周りと比べることが多くなります。
そして、
良くも悪くも守るべき責任が増え、
葛藤が生まれやすくなります。
4.仏教的な視点

仏教では、
それを「煩悩」と捉えます。
欲(得たい)、
瞋(守りたい)、
痴(本当の価値を見誤る)
が強くなると、
善悪の判断が曇ります。
悪を選択しても、
それを正当化します。
つまり、
言い訳です。
釈迦は、
「人は知っていても守れないことがある」と説き、
それを修行で少しずつ減らす道を示しました。
つまり、
知識として正しいことを知っていても、
実行は別問題なのです。
仏教は、
人生哲学でもあり、
実践の宗教です。
5.どう向き合うか

子供への道徳教育は無駄ではなく、
むしろ、
自分が理想から外れそうな時の「基準」になります。
自分が守れなかったときは、
それを「恥」や「罪悪感」として感じ、
「次はどう行動するか」
学びに変え、
行動することが大切です。
相談者

この世は結局のところ、
損得勘定で成り立っているということですか?
夫婦についても、
金銭的に、家事、性行為、世間体、さみしいから、
という損得勘定のような気がします。
会社も同僚も友達も、
付き合うことでメリットがあるあるからつながっていて、
メリットがなくなれば、
離れていく。
この世は、
すべてが損得勘定で流れているように感じます。
僧侶
あなたの感じていることは、
かなり多くの人が一度は抱く疑問です。
確かに現実を見れば、
この世の人間関係や社会の多くは損得勘定で
動いているように見えます。
ただし、
それが「すべて」かどうかは、
視点の置き方で変わります。
1.なぜ損得勘定が支配的に見えるのか

●生存本能
人間は生き延びるために、
有利な選択をするよう進化してきました。
お金・地位・安全は、
その延長線上にあります。
●現代社会の構造
資本主義は、
利益や効率を基準に人やモノが動く仕組み。
どうしても損得の尺度が前面に出やすくなります。
●心理の焦点化効果
一度「損得で動いている」と感じてしまうと、
人間関係の中で、
その側面ばかり目に入るようになります。
それを、
認知バイアスといいます。
2.仏教的な視点

●娑婆
仏教では、
利益・名誉・快楽・地位などを追い求める世界を、
「娑婆」と呼びます。
世間の関係は常に条件付きで、
条件が変われば離れていくのが自然です。
●縁(えん)
縁は「利益」だけでつながるものではなく、
善意・共感・信頼といった無形のものも含みます。
ただし、
これらも無常で変化します。
●布施(ふせ)
見返りを求めない与え方も存在します。
とくに親が子を育てる愛情や、
見知らぬ人への親切などは、
損得を超えた行為です。
3.夫婦や友人・仕事関係の現実

夫婦関係も確かに、
金銭・家事・性的相性・世間体などの損得要素は絡みます。
ただし、
それらがすべてではなく、
互いの信頼や安心感といった無形の価値も大きい。
仕事や友人関係も、
多くは「お互いにメリットがある限り続く」のが現実。
これは裏切りではなく、
契約や縁の性質に近いです。
4.損得勘定から離れる心の持ち方

●「損得勘定以外の価値」に目を向ける訓練
小さな善意、
無償の親切、
動物や自然との関わりなどを意識的に見る。
花は自分のために咲き、
他とは比べることはない。
動物は子供のために命を懸けて食べ物を与える。
そこに損得勘定は存在しない。
●自分から損得を超えた行為をする
見返りを求めない笑顔や言葉が、自分の世界を変えます。
笑顔やありがとうの言葉は、
お金を必要としない。
心、感情次第。
自分から笑顔や挨拶をすることは、
どちらが得になるでしょうか?
先手必勝!
自分からするほうが、
見えない得を獲得します。
●縁は無常であると理解する
「ずっと同じ関係でいられる」
という前提を手放すと、
離れていくことへの苦しみが減ります。
どんな形であれ、
別れがあることを心にとめておきます。
結論として

現実の多くは損得勘定で動いているが、
それだけではありません。
損得を超えた関係や行動は確かに存在しますが、
色々と経験した結果、
自分の軸を作れば、
裏切りに振り回されることはなくなります。
感情は自分で選択することができ、
感情は経験から学び育てることができます。
相談者

世間では損得勘定があるものの、
縁というものがあるということですね。
目に見える価値を魅力と言ってもいいんですが、
目に見えない価値や魅力があれば、
関係性は変わらないかもということですね。
損得勘定がなく、
目に見えない魅力で繋がっていたとしても、
離れてしまえば、
縁がなくなった。
縁が終わったと思えばいいということですか?
僧侶はい、
その理解は仏教的にも現実的にも正しいです。
1.損得勘定と「縁」の違い

●損得勘定は、
目に見える利益・条件で成り立つ関係です。
条件が変われば、
自然と関係も変わります。
●縁は、
目に見えない魅力・信頼・感情のつながりも含みます。
これは利益や条件を超えた要素ですが、
やはり無常なので変化する可能性はあります。
2.縁が終わるということ

仏教では、
「縁起」という考え方があり、
関係は原因と条件が揃って生まれ、
条件が変われば終わります。
離れてしまったときは、
「縁が切れた」のではなく、
「今回の縁の役割が終わった」
と捉えます。
そう思うことで、
腹が立つ感情が抑えられたり、
心にしこりを残さず手放しやすくなります。
終わった縁を無理につなぎとめようとすると、
ますます苦しみが増えます。
苦の原因を増長する行いです。
3.縁を大切にするための姿勢

損得勘定ではなく、
相手の存在そのものを喜ぶ関わりを心がける。
「今この瞬間の縁」を味わい、
未来を過剰に保証しようとしない。
あてにしない。
離れても感謝だけを残すように努めます。
まとめとして

損得を超えたつながりがあっても、
無常の理から逃れることはできない。
出会いがあれば、
別れは必然です。
偶然ということは絶対にありません。
裏切り行為で別れた場合は、
離れてしばらくは、
腹が立ち、
悔しい気持ちが続きますが、
その気持ちをシッカリと認め、
次は、
「縁の役割が終わった」
ことをシッカリと受けとめ、
そして次は、
なんとか感謝の気持ちを抱き、
その感謝のパワーで手放すことができれば、
心の安らぎに向かいます。