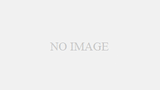「聞かれるまでは、自分の話をしない」という姿勢には、仏教的に見て非常に深い意味があります。それは単なる「謙虚さ」ではなく、**智慧と慈悲が備わった“沈黙の修行”**でもあるのです。
🧘♂️仏教的視点からの解説
🌿「自分の話をしない」=無我(むが)と我執(がしゅう)の手放し
仏教では、自分のことを誇示したり、主張したくなる心を「我執(がしゅう)=“自分中心の執着”」と呼びます。
この「聞かれるまでは話さない」という姿勢は、自分を立てようとする心を静め、“無我”に近づく実践です。
「自分がどう見られるか」ではなく、「相手に何が必要か」に意識が向いている状態です。
🌿「聞かれるまでは」=相手の心に寄り添う“慈悲の構え”
仏教では、「相手をよく観察し、タイミングを待つ」ことも慈悲の一つとされます。
特に「対機説法(たいきせっぽう)」といって、相手の心の状態や準備に応じて語るべきことを語るという教えがあります。
「語る」のではなく、「必要とされた時に差し出す」。それが仏の話し方。
🌿「沈黙」=言葉を慎む“正語”と“沈黙の智慧”
八正道のひとつに「正語(しょうご)=正しく語ること」がありますが、
これは「余計なことは語らない」「嘘・無駄・傷つける言葉を使わない」ことでもあります。
つまり、「聞かれるまでは語らない」は、言葉に対する深い敬意と慎みを持った智慧ある態度なのです。
💡 仏教的アドバイス
語る前に、まず聴く。これは“慈悲の入り口”です。
自分の話を求められた時に、はじめて言葉が力を持ちます。
沈黙は、心が整っている証。語らぬ智慧にこそ仏の光が宿る。
🧘♀️ 締めの言葉
「聞かれるまでは話さない」その沈黙には、深い慈悲と智慧がある。
それは仏が語るときを選んだように、語らぬことで相手を大切にする行いなのです。